EBITDA(利払い前・税引き前・減価償却前利益)とEBIT(税引前・金利支払前利益)は、企業の収益力を測る重要な指標ですが、「現金生成力」と「会計上の本業利益」という異なる視点で分析します。
EBITDAは設備投資の影響を除外し、現金ベースの収益力を評価するのに適しており、例えば製造業のM&A比較で有効です。
一方、EBITは借入金の影響を排除し、本業の純粋な営業効率を測定するのに役立ち、部門別の利益率分析に使用されます。
EBITDAとEBITにおいて、計算式の違い
EBITDAの構成要素
計算式営業利益 + 減価償却費 + 無形資産償却費
(例:営業利益100億円 + 減価償却費20億円 + 特許権償却費5億円 = EBITDA125億円)
現金支出を伴わない「非現金費用」を加算し、現金ベースの収益力を可視化。
具体例
工場設備が多い自動車メーカーでは、減価償却費が大きく、EBITDAが営業利益より高くなる。
EBITの構成要素
計算式営業利益(または 税引前利益 + 支払利息)
(例:税引前利益80億円 + 支払利息20億円 = EBIT100億円)
金利負担の影響を排除し、本業の収益性を純粋に評価。
具体例
多額の借入金がある不動産会社では、支払利息を加算して事業本来の収益力を測定。
実務的な違い
EBITDA
設備投資の影響を排除 → キャッシュフロー経営の評価
EBIT
会計上の利益ベース → 財務報告書との整合性
EBITDAとEBITにおいて、評価対象企業の違い
EBITDAが威力を発揮する業種
典型的な業種
製造業(自動車、鉄鋼)
インフラ事業(電力、ガス)
通信事業(基地局設備が多い携帯キャリア)
理由
多額の設備投資と減価償却費が発生するため、現金生成力を正確に評価する必要がある。
(例:鉄鋼メーカー同士を比較する際、工場建設時期の違いによる減価償却費の差を無視できる)
EBITが有効な業種
典型的な業種
ITサービス(SaaS企業)
小売業(借入金依存度が低い企業)
コンサルティング業
理由
無形資産の償却費が少なく、設備投資の影響が小さいため、会計上の利益を直接比較できる。
(例:クラウド企業の営業効率を、EBITマージンで部門別に比較)
業種別の指標活用例
| 業種 | EBITDA活用例 | EBIT活用例 |
|---|---|---|
| 航空会社 | 機体リース費用の影響を除外 | 路線別の収益性分析 |
| 製薬会社 | 研究開発費の償却影響を排除 | 製品ライフサイクル管理 |
EBITDAとEBITにおいて、分析目的の違い
EBITDAの主な活用場面
M&A評価
EV/EBITDA倍率で企業価値を算定(例:異業種間での比較が可能)
財務健全性分析
DSCR(債務償還余力倍率)の計算に使用(例:銀行融資の審査基準)
投資判断
設備投資サイクルの長い企業の現金生成力を測定(例:半導体工場の建設計画評価)
EBITの主な活用場面
事業効率の評価
営業利益率(EBITマージン)の算出(例:部門別の収益性ランキング作成)
経営陣の評価
金利負担の影響を除いた業績管理(例:事業部門長のKPI設定)
国際比較
会計基準の違いをある程度吸収(例:IFRSと日本基準の調整)
実務的な使い分け例
EBITDA
設備リース契約の意思決定
EBIT
新規事業の採算性検証
EBITDAとEBITにおいて、具体例で見る差異(深掘り版)
事例1:製造業A社(設備投資が多い)
| 項目 | 金額(億円) | 分析視点 |
|---|---|---|
| 営業利益 | 100 | 会計上の利益 |
| 減価償却費 | 30 | 過去の設備投資の影響 |
| EBITDA | 130 | 現金生成力 |
| EBIT | 100 | 本業の収益性 |
→ 投資家の視点
「EBITDA130億円は実際の現金流入に近い。設備更新に必要な資本支出(CAPEX)が50億円なら、自由現金流は80億円と計算できる」
事例2:IT企業B社(借入金が多い)
| 項目 | 金額(億円) | 分析視点 |
|---|---|---|
| 税引前利益 | 80 | 財務構造の影響を受ける |
| 支払利息 | 20 | 借入金のコスト |
| EBIT | 100 | 事業本来の収益力 |
→ 経営陣の視点
「EBIT100億円は事業の真の実力。金利20億円の負担が重い場合、借り換えでコスト削減を検討すべき」
EBITDAとEBITにおいて、まとめ表(実務活用版)
| 比較軸 | EBITDA | EBIT |
|---|---|---|
| 計算の焦点 | 現金生成力 | 会計利益 |
| 除外要素 | 減価償却費・無形資産償却費 | 支払利息 |
| 主な用途 | 設備投資の影響排除 | 財務構造の影響排除 |
| 適した業種 | 設備集約型産業 | 人的資本集約型産業 |
| 財務分析例 | EV/EBITDA倍率、DSCR | ROIC、EBITマージン |
| 弱点 | 資本支出を無視 | 減価償却方法の影響を受ける |
EBITDAとEBITにおいて、重要な補足(実務上の注意点)
EBITDAの落とし穴
CAPEX(資本支出)の盲点
減価償却費は過去の投資を反映するが、将来の設備更新費用は考慮されない
(例:EBITDAが高くても、多額のCAPEXが必要なら実際の現金余力は少ない)
償却方法の違い
定率法と定額法で減価償却費が異なるが、EBITDAはこれを無視する
(例:同じ設備でも会計方針でEBITDAが変動しないため、比較が容易)
EBITの注意点
減価償却の会計処理
資産の耐用年数や残存価値の設定が利益に影響
(例:耐用年数を短く設定するとEBITが低く表示される)
無形資産の扱い
のれん代や特許権の償却費がEBITを圧迫する
(例:M&Aで発生したのれん代償却費は本業の収益性を歪める可能性)
EBITDAとEBITにおいて、実務での使い分けチェックリスト
EBITDAを使うべき場面
設備投資の多い企業を比較する時
現金ベースの返済能力を評価する時
M&Aで異業種間の比較が必要な時
EBITを使うべき場面
部門別の収益性を評価する時
金利負担の影響を排除したい時
会計上の利益と連動した分析が必要な時
このように、EBITDAとEBITは「現金生成」と「会計利益」という異なるレイヤーで企業を評価します。
実務では、業種特性や分析目的に応じて、両者を組み合わせて使用することが重要です。
例えば
製造業であっても、EBITDAで現金流を把握しつつ、EBITで部門別の生産性を管理するといった併用が効果的です。
まとめ
EBITDAとEBITは、「何を評価したいか」で使い分けることが重要です。
EBITDAは設備投資が多い企業の現金生成力を比較する際や、債務返済能力を重視する際に有効です。
EBITは本業の営業効率を純粋に評価する際や、金利負担の影響を排除したい場合に適しています。
これら両指標は「車の両輪」であり、業種特性や分析目的に応じて、適切に組み合わせて活用することで、企業の財務状況をより正確に把握することが可能です。
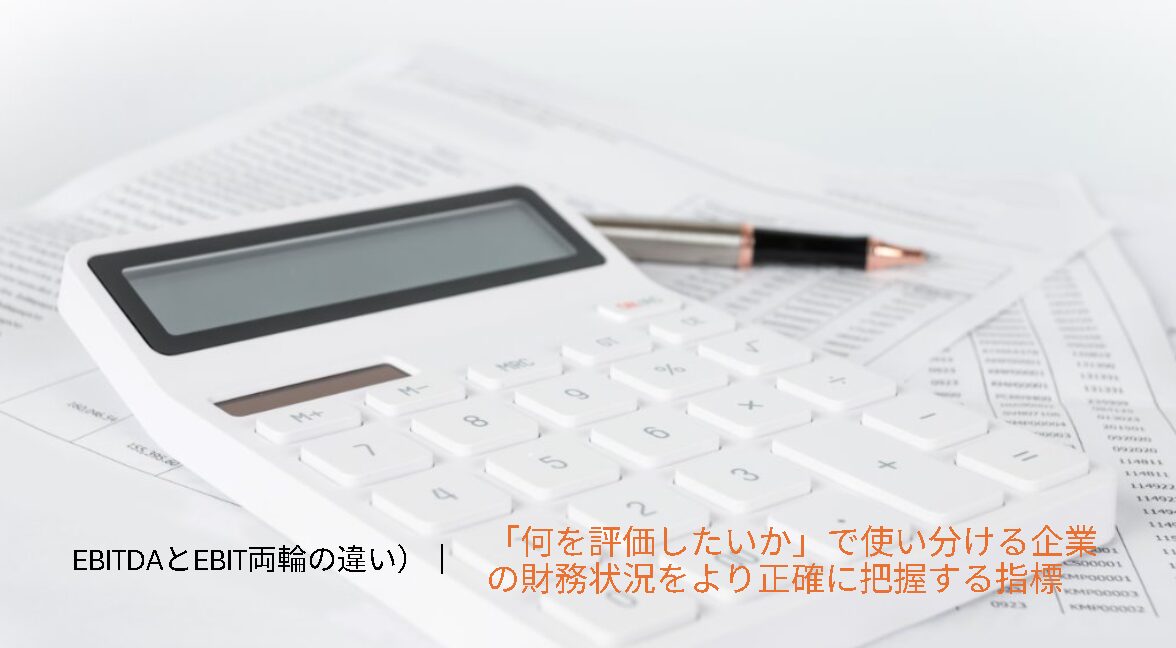
基準となる収益率-120x68.jpg)
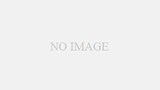
コメント