 収益分析
収益分析 企業のIR資料の活用|決算短信や決算説明資料を確認することでEPS(1株当たり純利益)活用
企業のIR(Investor Relations)資料は、投資家や株主に向けて企業が公開する重要な情報源です。これらの資料は、EPS(1株当たり純利益)を含む財務指標や経営戦略、将来の見通しなど、企業を総合的に理解するための貴重なデータを提...
 収益分析
収益分析  収益分析
収益分析  収益分析
収益分析 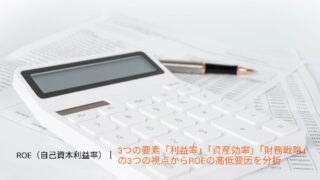 分析と検証
分析と検証  分析と検証
分析と検証  分析と検証
分析と検証 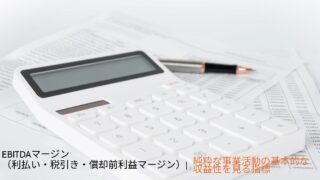 分析と検証
分析と検証 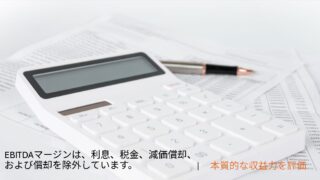 分析と検証
分析と検証