EPS(1株当たり純利益)は、企業の収益力を株主目線で分かりやすく示す重要な指標です。
しかし、株式数は新株発行や自社株買いなどで変動するため、単純な発行済株式数を使うだけでは実態を正確に反映できません。
そこで、EPSの計算では「自己株式を除いた期中平均株式数」を使うことで、株式数の増減による影響(希薄化や逆希薄化)を適切に織り込み、公平な利益配分を示すことができます。
EPS(1株当たり純利益)の計算において「発行済株式数」から自己株式を除いた期中平均株式数を用いる理由は、EPSの正確性と公平性を保つためです。
これは、希薄化リスクや逆希薄化といった株式数の変動がEPSに与える影響を適切に反映するためです。
希薄化リスクへの対応
希薄化リスクとは、企業が新たに株式を発行することで、既存の株主が持つ1株あたりの価値や利益が薄まってしまうことです。
たとえば、ストックオプションや新株予約権付社債が行使されると、従業員や投資家が新しい株式を手に入れます。
その結果、企業全体の利益は変わらなくても、株式の総数が増えるため、1株あたりの利益(EPS)は減少します。
これを正確に反映するため、EPSの計算では「期中平均株式数」を使います。
期中平均株式数とは、1年間の株式数の変動を平均して算出したものです。
こうすることで、株式数が増えた期間だけEPSが薄まる効果を正しく計算でき、投資家は実態に即したEPSを把握できます。
逆希薄化(自社株買い)への対応
逆希薄化は、企業が市場から自社の株式を買い戻すことで、発行済株式数が減り、1株あたりの利益(EPS)が増える現象です。
たとえば、企業が自社株買いを実施すると、市場に流通する株式が減ります。
利益を分け合う株主の数が減るため、同じ純利益でも1株あたりの取り分(EPS)は増加します。
ただし、買い戻された自己株式は会社が保有しているだけで、配当や議決権などの権利はありません。
EPSの計算では、こうした自己株式を分母から除外します。
これにより、実際に利益を受け取る株主だけでEPSを計算することができ、人為的にEPSを上げて見せる行為(見せかけの経営改善)を防ぎます。
逆希薄化があると、EPSが一時的に上昇するため、投資家はその背景も確認することが重要です。
公平かつ実態に即したEPSの算定
EPSは、企業の収益力を公平に示すための指標です。
そのため、株式数の変動や自己株式の存在を適切に考慮する必要があります。
期中に新株発行や自社株買いなどで株式数が増減する場合、単純に期末時点の株式数だけで計算すると、実際の株主が受け取る利益のイメージとズレが生じます。
そこで「期中平均株式数」を使うことで、1年間の株式数の変動を平均化し、EPSのブレを抑えます。
また、自己株式を除外することで、実際に利益配分の対象となる株主だけを分母に含めることができます。
これにより、企業が自社株買いなどの施策でEPSを人為的に操作するリスクを軽減し、投資家が企業同士を公平に比較できるようになります。
まとめ
EPSの計算で「自己株式を除いた期中平均株式数」を使うのは、
希薄化リスク(新株発行などで株式数が増えることでEPSが薄まる現象)と、
逆希薄化(自社株買いなどで株式数が減ることでEPSが上がる現象)
の両方を正確に反映し、
実際に利益を受け取る株主にとっての1株あたりの利益を、公平かつ実態に即して示すためです。
このようにすることで、EPSという指標が、企業の本当の収益力や株主価値を正しく表し、投資家が安心して企業を比較・評価できるようになります。
企業が意図的にEPSを操作した場合でも、その影響を適切に把握できるため、より信頼性の高い企業分析が可能になります。
このようなEPSの算出方法を理解することで、企業の本当の収益力をより公平に比較・評価できるようになります。

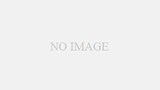
コメント