 分析と検証
分析と検証 1-3四半期ルールと季節調整|季節変動の影響を除去し、「データの本質を見極める」ために必須重点分析
「1-3四半期ルール」と「季節調整」は、企業の経営課題を的確に分析するための重要な方法です。1-3四半期ルールでは、売上高が3期連続で減少するなど同方向に変化した指標を重点分析し、一時的な変動と構造的な課題を区別します。一方、小売業の第4四...
 分析と検証
分析と検証  分析と検証
分析と検証  分析と検証
分析と検証 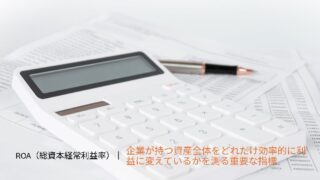 分析と検証
分析と検証  分析と検証
分析と検証  分析と検証
分析と検証 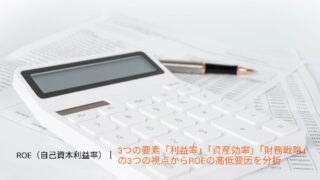 分析と検証
分析と検証  分析と検証
分析と検証 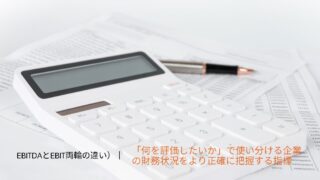 分析と検証
分析と検証 基準となる収益率-320x180.jpg) 分析と検証
分析と検証