ROE(自己資本利益率)は、企業が株主の資金をどれだけ効率的に利益に変えたかを示す重要な指標です。
単純な計算式で算出する方法と、3つの要素に分解して分析する方法の2つがあります。
基本式は収益力を直感的に把握するのに適していますが、分解分析では「利益率」「資産効率」「財務戦略」の3つの視点からROEの高低要因を深掘りできます。
本解説では、両者の違いと具体的な活用方法をわかりやすく整理します。
ROE(自己資本利益率)の基本計算式と分解分析の違い
基本計算式:ROEの単純算出
計算式
ROE=当期純利益自己資本×100 (%)
株主が投資した資金(自己資本)に対し、企業がどれだけの利益を生み出したかを示す指標です。
例
自己資本100億円で当期純利益10億円の場合、ROEは10%となります。
活用方法
企業の収益力を単純比較する際に使用します。
投資家が「株主資本の運用効率」を評価する基本的な指標として活用されます。
分解分析(デュポンシステム):ROEの3要素
計算式
ROE=売上高純利益率×総資産回転率×財務レバレッジ
売上高純利益率
売上高当期純利益
総資産回転率
売上高総資産
財務レバレッジ
総資産自己資本
売上高純利益率
売上に対する純利益の割合(収益性)
総資産回転率
資産をどれだけ効率的に売上に結びつけたか(資産効率)
例総資産200億円で売上高100億円 → 0.5回転
財務レバレッジ
自己資本に対する総資産の比率(借入金活用度)
例
自己資本100億円、総資産200億円 → 2倍
活用方法
課題特定
ROEが低い原因を3要素に分解して分析します。
例
売上高純利益率が低い → コスト削減や価格戦略の見直しが必要。
例
総資産回転率が低い → 在庫削減や設備活用の効率化が必要。
例
財務レバレッジが低い → 適度な借入で資金調達を検討。
戦略立案:各要素のバランスを調整し、ROEを最適化します。
基本式と分解式の違い
| 項目 | 基本式 | 分解式 |
|---|---|---|
| 目的 | 収益力の単純比較 | ROEの要因分析と改善策の特定 |
| 視点 | 株主資本の運用効率 | 収益性・資産効率・財務戦略の多角的分析 |
| 活用例 | 業種間や競合他社との比較 | 自社の内部課題発見と戦略的なROE向上策の立案 |
具体例で見る分解分析
ケーススタディ
A社
売上高100億円、当期純利益10億円、総資産200億円、自己資本100億円
売上高純利益率
10%
総資産回転率
0.5 回転
財務レバレッジ
2倍
ROE
10%×0.5×2=10%
改善策
売上高純利益率を12%に向上
コスト削減や高付加価値商品の導入。
総資産回転率を0.6回転に改善
在庫削減や設備稼働率向上。
財務レバレッジを2.5倍に調整
適度な借入で投資を拡大。
→ 新ROE:12%×0.6×2.5=18%
まとめ
基本式
ROEは「株主資本の運用効率」を簡潔に評価する指標です。
分解式
ROEを3要素に分解し、収益性・資産効率・財務戦略の課題を特定します。
活用のポイン
分解分析で弱点を明確化し、具体的な改善策を立案。
過度なレバレッジ依存や利益率低下に注意し、バランスの取れたROE向上を目指す。
投資家は分解分析を通じて企業の戦略的健全性を評価し、経営陣は内部課題の解決に役立てることができます
ROEの基本式は「結果」を、分解式は「原因」を分析するツールです。
投資家は基本式で業界内のポジションを確認し、経営陣は分解式で収益性・効率性・財務戦略のバランスを最適化します。
例えば、利益率が低い企業はコスト削減を、資産回転率が低い企業は在庫削減を、レバレッジが低い企業は適度な借入を検討します。
両者を組み合わせることで、持続可能なROE向上を実現しましょう。
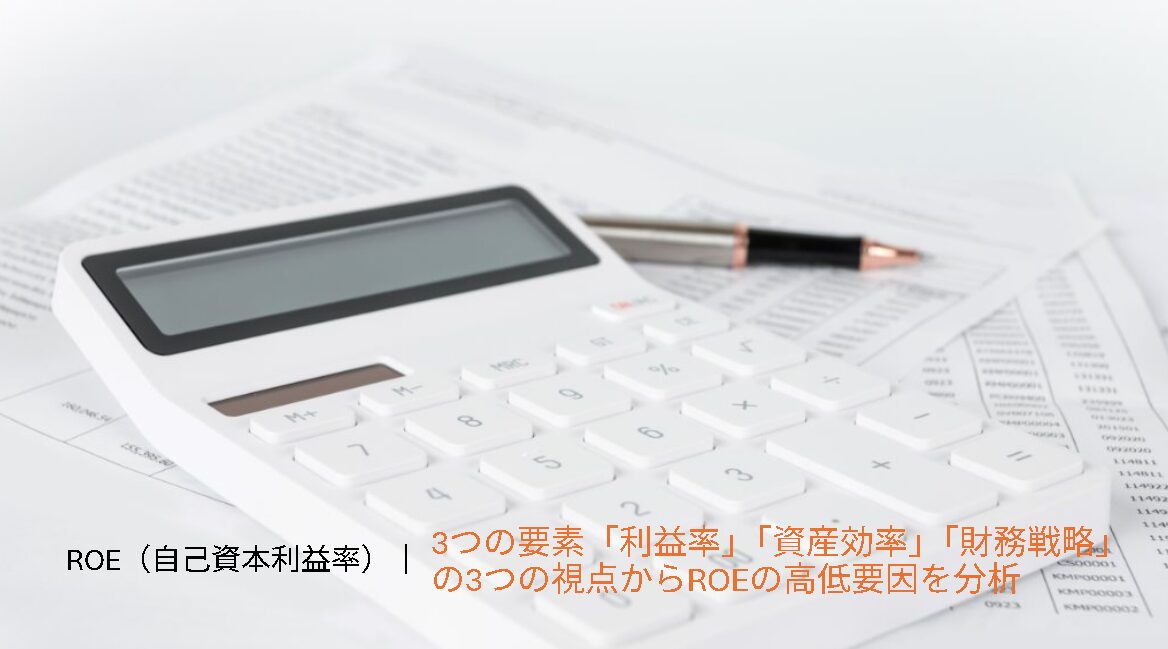
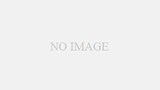
コメント